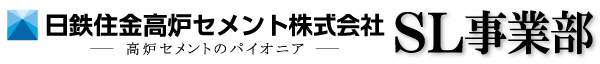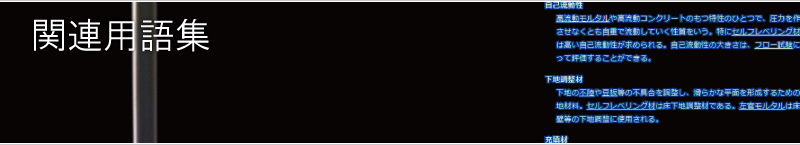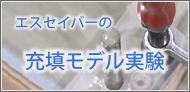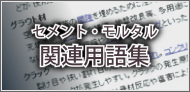セメント・モルタル関連用語集
数字・記号
- J漏斗(Jロート)
- モルタルの流動性試験に使用される細長の漏斗試験器。主に粘性(塑性粘度)を表す指標となり、流下時間が短いほど粘性が低い。ただし総合的な流動性を粘性だけで表現することはできないため、必ずしも粘性が低い方が流動性が高いとは限らない。フロー試験等の他の試験方法と併せて評価する必要がある。
- J14漏斗(J14ロート)
- J漏斗のひとつ。主にグラウト材の流動性の評価試験に用いられる。流出口寸法はφ14mm。土木学会規準、充てんモルタルの流動性試験方法(JSCE-F 541)に規定されている。
- JP漏斗(JPロート)
- J漏斗のひとつ。主にPCグラウトの流動性の評価試験に用いられる。J14漏斗の流出口の先に30mmの直管が付いた形状になっている。土木学会規準、PCグラウトの流動性試験方法(JSCE-F 531)に規定されている。
- PCグラウト
- プレストレストコンクリート(ポストテンション方式)において、PC鋼材とコンクリートとの付着およびPC鋼材の防錆を目的として、PC鋼材とシースとの間に注入するグラウト材。セメントミルクに近い低粘性のスラリーのほか、曲げ下がり部の先流れを防止する高粘性のものがある。
- P漏斗(Pロート)
- モルタルやペーストの流動性の評価試験に用いられる漏斗試験器。流出口はφ13mmで流出口の先に38mmの直管がある。容量はJ漏斗よりも大きく、粘性の非常に低いスラリーの試験に適している。土木学会規準、プレパックドコンクリートの注入モルタルの流動性試験方法(P漏斗による方法)(JSCE-F 521)に規定されている。
- SL材
- セルフレベリング材を参照。
ア行
- アジテータ車
- 生コン車を参照。
- 圧縮強度
- 材料のもつ特性のひとつで、圧縮荷重に対して材料が耐えられる最大応力。荷重(力)を面積(載荷断面積)で割ったもので表され、コンクリート分野では[N/mm2]の単位が用いられる。セメント硬化体は時間の経過とともに強度が伸びる特徴があるので、28日材齢の圧縮強度を材料の性質を示す指標とする場合が多い。
- アンカーグラウト
- アンカーボルトをコンクリート等の既設構造体に定着させるために使用されるグラウト材。アンカーボルトに作用する引抜き力に耐えられるだけの接着力、せん断耐力を要求される。最近では、カプセル容器に入ったタイプのアンカーグラウトが使用されることが多い。
- 打ち下ろし
- 高さのある構造物を打設する際、上部からコンクリートやグラウト材等を流し込む、または落とし込むこと。材料分離が発生しやすく、また狭隘部を充填しにくい場合がある。
- エアモルタル
- モルタルに発泡させた気泡を混入したもの。気泡モルタル、発泡モルタル等ともいう。通常のモルタルに比べて密度および圧縮強度が非常に小さい特徴がある。エアモルタルで作られたグラウト材を気泡グラウトという。水との接触あるいは時間経過によって脱泡する場合がある点に注意が必要。
- 温暖化
- 地球温暖化。一般的には、人間の産業活動に伴って排出される温室効果ガスが主原因と考えられている。セメントの製造においては、石灰石の焼成時に主要な温室効果ガスである二酸化炭素を多量に放出するため、高炉スラグやフライアッシュを用いた混合セメントは温暖化への環境負荷が小さい材料であるといえる。
- 温度ひび割れ
- セメントは水と混合されると水和反応を起こし、その際に水和熱を生じる。このため、大断面の部材では内部の温度上昇が大きくなり、表面部との温度差または外部からの拘束によってひび割れが発生しやすくなる。温度ひび割れの防止には、セメント量を少なくする、あるいは水和熱の低いセメントを使用することが効果的。
カ行
- 可使時間
- 材料の有する特性のひとつで、凝固や分離をすることなく、施工が可能な程度の流動性を保つ時間をいう。可使時間が長いほど凝結・硬化は遅くなる。スラリー等には粘性があるため、SL材を大空間に打設する場合やグラウト材を小間隙に充填する場合には特に十分に長い可使時間が必要。
- 風クラック
- セルフレベリング材に発生する不具合のひとつ。スラリーの表層膜が通風によって引っ張られ、膜が切れること。寄せられてしわ状になった部分を風しわという。風クラックは表層(数十〜数百μm)クラックであり、セルフレベリング材の硬化後の耐久性にはほとんど影響がないと考えてよい。
- 風しわ(風皺)
- セルフレベリング材に発生する不具合のひとつ。スラリーの表層膜が通風によって寄せられ、しわ状になること。引っ張られた表層膜が切れた部分を風クラックという。風しわはケレン程度で取り除くことができるが、仕上げ材を貼るのに支障がなければそのまま貼っても大きな問題はない。
- カチオン材
- プラス電荷に帯電させることで付着力を強化した接着材。コンクリート等の構成材料は、通常、マイナス電荷を帯びている(アニオン)ため、プラス電荷(カチオン)を帯びた接着材の方が強い接着強度が得られる。
- 間隙
- 物体と物体の間のすきま。物体同士の固定や力の伝達等を目的として、間隙を埋める材料が充填材(グラウト材)である。
- 乾燥収縮
- 物体の体積が乾燥によって縮む現象。コンクリートに限らず、多孔質な材料は水分蒸発によって乾燥収縮が発生する。セルフレベリング材が硬化後に乾燥を受けると、乾燥収縮によってクラックが発生する場合がある。硬化前に急激な乾燥を受けた場合には、プラスティックひび割れが発生することが多い。
- 気泡グラウト
- エアモルタルで作られたグラウト材。発泡グラウトともいう。通常のセメント系グラウト材に比べて、著しく密度(1.0kg/m3程度)および圧縮強度(数N/mm2以下)が小さい。地下壕の埋戻しや廃棄管の中込め充填、各種裏込め等に適している。
- 凝結
- セメントの水和反応により、セメント粒子同士が集合して凝集し、流動化しなくなる現象。凝結時間の測定方法は、JIS R-5201附属書1(セメントの試験方法-凝結の安定性と測定)、JIS A-1147(コンクリートの凝結時間試験方法)に規定されている。凝結時間が短いほど速乾性があるが、可使時間は短くなる。
- 杭周固定液
- コンクリートパイルの施工時に使用されるスラリーで、根固め液注入後に掘削孔に注入する。掘削孔の造成および杭と地盤との支持力の強化を目的として使用する。セメントミルクなどが使用される場合が多い。
- グラウト材
- 空洞や隙間等の間隙を埋めるために注入するスラリー状の材料。充填材。構造物の空隙充填の他、クラックの補修、地盤改良等、多用途に使用される。間隙を充填しなければならない必要上、無収縮やノンブリーディングといった性質が求められる。
- クラック
- 裂け目や狭い割れ目のこと。ひび割れ。コンクリート等のセメント硬化体は多孔質であるため、クラックが発生しやすい。クラックの発生原因は、施工や養生不良、温度上昇、乾燥収縮などのほか、アルカリ骨材反応や塩害による鉄筋の腐食によるものなど、極めて多岐に渡る。
- グリーン購入法
- 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律の通称。同法では、環境負荷低減に資する製品やサービスの調達を推進している。高炉セメントは、特定調達品目に指定されている。
- コーキング材
- 水密等を目的として目地等に詰めるペースト状の材料。シーリング材ともいう。
- 鋼板巻立て工法
- 主にコンクリート製の柱や橋脚等の耐震補強を目的とした補強工法のひとつ。柱部材を鋼板で巻き立ててその間隙をグラウト材で充填し、部材断面を大きくしてせん断および曲げ耐力を向上させる。橋脚耐震補強の主流となっている。
- 高強度
- 一般的なものよりも強度レベルが高いこと。建築学会の高強度コンクリート施工指針(案)によれば、圧縮強度の設計基準強度が36N/mm2を越え120N/mm2以下のコンクリートを高強度コンクリートとしている。
- 降伏値
- レオロジー特性のひとつ。生コンクリートやスラリー等のビンガム流体では、ある一定以上の力を与えないと流動し始めない性質をもち、この時の力の大きさを降伏値という。スランプ試験やフロー試験などは、降伏値を評価する代表的な試験である。降伏値が小さいほど流動性は大きい。
- 高流動モルタル
- 左官材等に使用される通常のモルタルよりも流動性が高いモルタル。高性能減水剤や増粘剤等を添加することで機能性が高められている。セルフレベリング材やセメント系グラウト材の多くは高流動モルタルである。
- 高炉スラグ
- 銑鉄を製造する溶鉱炉(高炉)から、銑鉄とともに溶融状態で産出される副産物。カルシウム、シリカ、アルミナ等、セメントに類似した化学成分を持っている。溶融状態のスラグを水で急冷すると砂状に固化する(水砕スラグ)。急冷しない徐冷スラグは、セメント原料や路盤材等に使用される。
- 高炉セメント
- 高炉スラグを原料に用いた混合セメントのひとつ。高炉スラグの含有量の違いによって、A種(5〜30%)、B種(30〜60%)およびC種(60〜70%)に分類されている。混合セメントの製造には石灰石の焼成プロセスがないので、温暖化ガスの発生を抑制でき、グリーン購入法の特定調達品目に指定されている。
- 骨材
- モルタルやコンクリートの構成材料のひとつ。骨材の寸法によって細骨材(5mm以下の砂)と粗骨材(5mmより大きい砂利)に分けられる。コンクリートの場合、全骨材容積は全容積中の6〜7割程度を占める主要な材料である。モルタル製品の細骨材には、ケイ砂や石灰石細骨材が使用されている場合が多い。
- 固定プラント式
- セルフレベリング材等の供給方式のひとつ。専用プラントで練り混ぜたスラリーを生コン車で現場まで運搬する方式。対して、原料タンク・計量機・ミキサを搭載した専用車が施工現場でスラリーを練り混ぜる方式を移動プラント式と呼ぶ。また適切な割合で混合した原料を袋詰めし(プレミックス)、現地で水と混練するものを、袋物と呼ぶ。
- コンクリート
- 水とセメントと骨材(細骨材+粗骨材)を混合した建設材料のひとつ。任意の造形、強度設計ができ、比較的安価なため、様々な用途に使用されている。
- コンシステンシー
- コンクリート等の材料の変形性や流動性の度合いをいう。代表的なコンシステンシー評価試験に、コンクリートのスランプ試験がある。ただし、フレッシュコンクリートやスラリーは粘性と塑性の性質をあわせもち単純にモデル化できない材料であるため、単一の試験からコンシステンシーのすべてを評価することはできない。
サ行
- 材料分離
- モルタルやコンクリートを構成する材料(水,セメント,骨材等)が分離し、均質な状態でなくなる現象。粘性が低いほど発生しやすい。流動や落下等の外力によって分離しやすくなるが、材料の密度差によって静置状態でも発生する。材料分離が発生すると、強度や弾性、膨張収縮率等が均質でなくなるため、劣化が生じやすくなる場合がある。ブリーディングは材料分離のひとつ。
- 材齢
- コンクリート等を打設してからの経過時間。セメントの水和反応は時間の経過とともに徐々に進行していくため、材齢とともに圧縮強度は増進する特徴をもつ。設計基準強度等の材料の特性では、28日材齢を指標とする場合が多い。
- 逆打ち(さかうち)
- コンクリート等を打ち込む際、通常は既設コンクリートの上に新しいコンクリートを打設するが、既設コンクリートの下側に新しいコンクリートを打設することを逆打ちという。ブリーディングや沈下によって既設コンクリートとの継ぎ目が一体化しにくい。空気溜まりも発生しやすく、空気抜きを設けるなどの施工面でも注意することが必要。グラウト材を逆打ちする場合には、ノンブリーディングおよび無収縮であることが必須。
- 左官材
- 日本建築で古くから行われている土壁や漆喰等を鏝で仕上げる塗り仕上職人を左官といい、左官の使う珪藻土や漆喰等の材料を左官材という。近年では、左官業がモルタル仕上げに従事することから、モルタル製品等の鏝ならしを必要とする材料(左官モルタル)も左官材と呼ばれている。
- 左官モルタル
- 鏝ならしを行うモルタル製品。セルフレベリング材は自己流動性があり、鏝ならしが必要ないため、左官モルタルとは呼ばないのが普通である。
- 仕上げ材
- 床や壁、天上等を覆う、建築物の内外装に使用される表面材料。仕上げ材には、フローリングやタイルのような張り付けるものと、漆喰のように塗り仕上げのものがある。一般的なセルフレベリング材は床下地調整材であり、乾燥収縮の防止等のために仕上げ材で覆う必要がある。
- 自己収縮
- コンクリートやモルタルに発生する現象のひとつ。セメントの水和の進行に伴って内部の水分が消費されていくと、部材内部は乾燥状態(自己乾燥)に陥るため、体積収縮を起こす。この現象を自己収縮という。水セメント比が小さく、断面寸法の大きいほど自己収縮は大きくなりやすい。無収縮グラウト材は、自己収縮を補償し硬化後の無収縮を確保したグラウト材である。
- 自己流動性
- 高流動モルタルや高流動コンクリートのもつ特性のひとつで、圧力を作用させなくとも自重で流動していく性質をいう。特にセルフレベリング材には高い自己流動性が求められる。自己流動性の大きさは、フロー試験によって評価することができる。
- 下地調整材
- 下地の不陸や豆板等の不具合を調整し、滑らかな平面を形成するための下地材料。セルフレベリング材は床下地調整材である。左官モルタルは床や壁等の下地調整に使用される。
- 充填材
- グラウト材を参照。
- 充填性
- グラウト材のもつ特性のひとつで、間隙に浸入してすきま無く埋め、密閉させる性質をいう。一般的に、流動性が高いほど、また流動性の保持時間(可使時間)が長いほど充填性は高い。
- 樹脂モルタル
- 合成樹脂と骨材とを混合したモルタル。通常のモルタル(セメントモルタル)とは異なる。合成樹脂とセメントを使用するポリマーセメントモルタルとも異なる材料だが、混同されていることもある。止水を目的としてエポキシ樹脂を組み合わせ床仕上げに薄塗りする、といった使われ方をする場合が多い。
- 水砕スラグ
- 溶融状態の高炉スラグを水で急冷してできた砂状のスラグ。非晶質(ガラス質)で、刺激剤のもとで水と反応して硬化する潜在水硬性をもつ。高炉セメントの原料やコンクリート用骨材(スラグ細骨材)、覆砂材等の用途に使用されている。高炉スラグ微粉末は、水砕スラグを微粉砕したものである。
- 水中不分離性
- コンクリートやモルタルが水中でも分離せず一体化した状態を保つことができる性質をいう。水中不分離性の確保には、増粘剤等の混和剤を用いて粘性を高めている場合が多い。一般的に、粘性が高いほど水中不分離性は高くなる傾向にある。グラウト材の充填において、間隙が湛水している場合や充填後に浸水がある場合などでは、高い水中不分離性が必要になる。
- 水平流動性
- スラリー等の水平方向への流動性をいう。水平方向へは重力が作用しないため、自重のヘッド圧(水頭圧)のみで流動する自己流動性が高いほど水平流動性も高い。水平方向に流動する際には砂落ちなどの材料分離が起こりやすく、適度な粘性を必要とする。
- 水和熱
- セメントと水との水和反応に伴う発熱。マスコンクリートの温度ひび割れの原因となる。反応の速い早強型のセメントほど水和熱は大きくなり、低熱セメントや混合セメントでは小さくなる。
- スラリー
- 固体の粒子が液体中に浮遊し、泥状の懸濁液になっている状態をいう。硬化していない高流動モルタルやセメントミルクなどはスラリーである。
- 石こう(石膏)
- 硫酸カルシウムを主成分とする鉱物。結晶水の量の違いによって、無水石こう(硬石膏)、半水石こう(焼石膏)、二水石こうなどがある。セメント分野では、凝結のコントロールや膨張材として、二水石こうおよび無水石こうが使用されている。いずれも天然のものと人造のものがある。
- 接着強度
- 下地と下地調整材、下地調整材と仕上げ材等の異なる材料同士の接着力の度合いを示したもの。破断した時の荷重(力)を面積(載荷断面積)で割ったもので表され、[N/mm2]の単位が用いられる。一般的には、材齢14日での値が接着強度の指標となる場合が多い。
- セメント
- 水と混合すると固化する粉体の総称で、一般的には建設用のポルトランドセメントまたは混合セメントを差す。ポルトランドセメントには、普通、早強、超早強、中庸熱、低熱などがあり、混合セメントには高炉セメント、フライアッシュセメントなどがある。
- セメントミルク
- セメントと水とを混合してミルク状の懸濁液としたもの。セメントスラリー。特殊な混和剤を混入する場合もある。非常に粘性が小さい。グラウト材、地盤改良材、コンクリートパイルの杭周固定液等に使用される。
- セルフレベリング材
- 建設材料のひとつで、自己流動性をもった床下地調整材。SL材、レベリング材ともいう。セメント系と石こう系とがある。左官による直押さえと比較すると、軽いトンボ均し程度で平滑・平坦な水平面を形成できるため、水平精度が高く施工が省力化される。大空間を施工する際には、特に高い水平流動性と適度な可使時間が必要となる。
- 潜在水硬性
- 高炉スラグのもつ性質のひとつ。高炉スラグは水と混合しただけでは硬化しないが、アルカリ刺激剤の刺激によって水和反応が起こり硬化する性質をもつ。高炉セメントは、セメントの水和によって生成したCa(OH)2が高炉スラグの刺激剤となっている。なお、フライアッシュ等の水和はポゾラン反応であり、潜在水硬性とは異なる。
- 塑性
- 物質の変形や流動のしやすさの状態を示すもので、力を加えて変形させた後に力を取り除いても変形が完全に戻らない性質をいう。フレッシュコンクリートやモルタルは塑性の性質をもつ流体であるが、硬化が進むと徐々に弾性(除荷すると変形が元に戻る)の性質を示すようになる。
- 塑性粘度
- レオロジー特性のひとつ。塑性流体のもつ粘り強さの度合いをいい、塑性粘度が高いほど、一定の力が加わったときの変形速度が小さくなる。漏斗試験は、塑性粘度を評価する代表的な試験である。スラリーの塑性粘度は、温度が高くなるほど低下し、温度が低くなるほど高くなる性質がある。
- 速乾
- 硬化の早さを示すもので、モルタル製品では、水と混合してから数十分〜数時間以内で硬化するタイプを速乾型という。速乾型は、型枠の早期脱枠や次工程の作業に速やかに移行できる等の工期上の利点がある。反面、流動性を長時間保持できず、可使時間は著しく短くなる。
- 外床
- ベランダや外廊下などの室外の建築床をいう。一般的に、外床では水勾配が必要とされるので、床下地調整材にはセルフレベリング材を使用できず(水平に仕上がってしまうため)、左官モルタルが使用される場合が多い。
タ行
- ダイラタンシー
- 粘塑性流体の力と変形性との関係性を示すもので、力が加わると流動性を失って液状から固体状に変化し、抵抗が大きくなる現象をいう。チキソトロピーの逆の性状。身近なダイラタンシーの例では、水溶き片栗粉がある。
- 耐久性
- 長い時間が経過しても、大きな変質、劣化を生じず、材料および構造物に要求される性能を確保できる度合いをいう。
- 耐震性
- 地震に対して、構造物が破壊、損傷せずに耐えられる度合いをいう。既存の構造物について耐震性を向上させる技術が耐震補強である。耐震に関連する用語には、免震、制震などがある。耐震は地震外力を受けても倒壊しないこと、免震は地震外力を受けないようにすること、制震は地震外力のエネルギーを吸収して減衰させることを表す。
- 耐震補強
- 耐震基準を満たさない構造物に対して基準と同等以上の耐震性を確保するよう、耐震性を向上させるための補強を施すことをいう。耐震補強の一例には、壁や開口部を補強するブレース工法、柱を補強する鋼板巻立て工法などがある。
- タッピング
- 締め固めるまたは馴染ませる等の目的のために、コンクリートやモルタルに軽い振動を与えたり、型枠を軽く叩くことをいう。
- チキソトロピー
- 粘塑性流体の力と変形性との関係性を示すもので、力が加わると流動性が大きくなって固体状から液状に変化し、抵抗が小さくなる現象をいう。チクソトロピー、チキソ性も同じ。ダイラタンシーの逆の性状。高分子系の増粘剤を添加したモルタル製品では、チキソトロピーを示すものが多い。身近なチキソトロピーの例では、ケチャップがある。
- 低熱
- セメントの水和熱が低いこと、またはモルタルやコンクリートの発熱が小さいことをいう。コンクリート等を低熱型にするためには、水和熱の低いセメントを使用したり、コンクリートのセメント量を少なくする必要がある。
- 天端(てんば)
- 建造物の最上端。上端(うわば)ともいう。基礎天端は、基礎の上端のこと。
- ドライアウト
- モルタル等のセメント系材料を塗布したり打継ぐ場合に発生する不具合のひとつ。下地のコンクリート等が乾燥している場合、塗りつけたモルタルの水分が吸われて接着面が乾燥状態になり、セメントの水和が阻害され、硬化不良や接着不良が発生する。また直射日光や通風によって下地が異常に乾燥したような場合もドライアウトが発生することがある。ドライアウトを防ぐためには、下地を十分に吸水させておくことや、吸水調整剤(プライマー等)を塗布するなどの注意が必要になる。
- トレミー工法
- 主に、コンクリートやグラウト材などを水中等に打設するときに使用される工法。水中に輸送管(トレミー管)を装入した状態でコンクリート等を送り込み、徐々に管を引上げて連続的に打設するのが特徴。トレミー工法で打設する場合、コンクリート等の材料には高い水中不分離性が求められる。
ナ行
- 長さ変化試験
- コンクリートやモルタルの膨張収縮を測定する試験方法のひとつ。測定方法には、コンパレータ法、コンタクトゲージ法、埋め込みゲージ法などがある。
- 生コン車
- 生コンプラントで製造したフレッシュコンクリートを現場まで輸送するためのトラック。生コンが材料分離、凝結しないようにするために、緩やかに攪拌する回転式傾動ドラムを装備している。アジテータ車ともいう。ドラム内でコンクリートを混練、製造可能なミキサー車(移動式ミキサ)とは異なるが、一般的には生コン車もミキサー車と呼ばれることが多い。
- 生製品
- まだ固まっていないフレッシュの状態で納入するコンクリートやモルタルをいう。生コンクリートは最も一般的な生製品のひとつ。
- 生タイプ
- まだ固まっていないフレッシュの状態で納入する製品のことで、主にモルタル製品をスラリー供給する様式を差す言葉としても使われる。生製品、生スラリーなどともいう。生タイプでないモルタル製品は、袋物と呼ばれる。
- 布基礎
- 建築基礎の種類のひとつ。一般的な戸建住宅の基礎は、大きく布基礎とベタ基礎に分けられる。建物の外周・内壁部分のみ基礎工事を行い、幅が狭く延長が長い状態の基礎を布基礎という。対して、建物全体に基礎工事を行うものがベタ基礎。
- 塗り床
- 床の仕上げ材にエポキシ等の合成樹脂を用いて塗り仕上げとしたものをいう。じん性に富み、耐久性が高い。工場や倉庫等、フォークリフトが走行するような高強度が求められる部位にセルフレベリング材を施工する際は、塗り床仕上げにする場合が多い。
- 練混ぜ水量
- プレミックスしたモルタル(袋物)と混合する水の量。混練水量ともいう。プレミックスモルタルは、適切なワーカビリティが得られるように、練混ぜ水量が指定されている場合が多い。この場合、袋の裏面に所定水量が記載されている。所定の水量範囲を越えた水量で練り混ぜると、適切なワーカビリティが得られなくなるだけでなく、ブリーディングが発生するなどの不都合が起こりやすい。
- 粘性
- 液体のもつ粘りの性質をいう。生コンクリートやスラリーの性質で粘性という言葉が使われる際は、塑性粘度を意味している場合が多い。モルタル製品では、材料分離を防ぐために増粘剤を混入して適度な粘性を確保しているものが一般的である。
- ノンブリーディング
- 材料のもつ性質のひとつで、ブリーディングの発生がないことをいう。グラウト材にブリーディングが発生するとブリーディング部分が空隙として残ってしまうため、グラウト材にはノンブリーディングが要求される場合が多い。特に水平充填や逆打ちを行う場合には必須性能のひとつである。
ハ行
- 白華
- コンクリートやモルタルの表面に浮き出る白い生成物。エフロレッセンスともいう。冬季や雨季に発生しやすい。白色生成物の主成分は炭酸カルシウムであり、白華が生じても構造上や環境上の問題はない。ただし、セルフレベリング材に生じた白華は仕上げ材との付着を妨げる可能性があるため、除去する必要がある。
- パッド材
- 機械装置の台座や鉄骨等を据え付ける際に使用する支持材料。セメント系のものは、高強度タイプのモルタル製品が袋物として市販されている。
- ハンドミキサー
- 袋物のモルタル製品などを現場で練り混ぜる時に使用する携帯型のミキサー。袋物の練混ぜは、所定の練混ぜ水量を入れたバケツに、ハンドミキサーで混合しながら袋物製品を少しづつ投入して行う。ハンドミキサーの羽根および回転数は、練り混ぜる製品に適したものを用いる。
- ひび割れ
- クラックを参照。
- ビンガム流体
- 粘性と塑性の性質をもち、ある一定以上の力(降伏値)が加わらないと流動し始めない流体。生コンクリートやスラリーはビンガム流体である。その他の身近なビンガム流体の例では、バターがある。
- 袋物
- 袋に梱包された製品の一般的な呼称。モルタル製品は、水以外の材料をプレミックスした状態で袋に梱包し、袋物として流通しているものが多い。袋物ではない、水と混合したスラリーの状態で納入するモルタル製品は、生製品やスラリー製品などと呼ぶ。
- プライマー
- 塗装などの際に、下地との付着を高めるために下塗りする塗布材料。シーラーともいう。セルフレベリング材を施工する際には、下地からの吸われによってドライアウトが発生するため、施工前にプライマーを塗布する必要がある。多くの場合、プライマーは専用のものがあるので、これを所定の手順に従って塗布する。
- プラスティックひび割れ
- 硬化する前または硬化の極初期に発生する乾燥収縮ひび割れ。硬化前に急激な乾燥を受けると、水分の蒸発量がそのまま体積収縮量となる(プラスティック収縮)ため、激しいひび割れが発生することがある。夏季や直射日光が当たる場所、通風の大きい場合など、乾燥が激しい環境で特に発生しやすい。
- 不陸(ふりく)
- 床などの平滑であるべき面が、平らでなく凹凸のある状態をいう。ふろくともいう。床の下地には完全な平滑面を求めることが難しいため、凹部を埋める不陸調整や、床面全面を平らにする下地調整などを行う必要がある場合が多い。セルフレベリング材は、不陸のない平滑面を形成するための下地調整材である。
- ブリーディング
- 材料分離のひとつ。構成材料の密度差によって、最も軽い水が上部に移動する現象。粘性が低いほど発生しやすい。グラウト材においては、ブリーディングした部分が空隙となって残ってしまうため、ノンブリーディングでなければならない場合が多い。全容積に対するブリーディング水量の比率を、ブリーディング率という。
- ブレース工法
- ブレースとは斜材(斜め部材)のことで、ブレースによって開口部や壁の補強を図る耐震補強工法のひとつ。ブレースを嵌め込むことで地震による水平方向の耐力が向上する。躯体とブレースとは、アンカーボルト打設やグラウト材の充填によって、一体化を図る。
- プレパックド工法
- コンクリートを打設する際、型枠にあらかじめ粗骨材(砂利)のみを詰めておき、粗骨材の隙間にグラウト材やモルタルを注入する工法。出来上がったコンクリートはプレパックドコンクリートと呼ばれる。グラウト材の注入は最下部から上に向かって打ち上げる逆打ちによって行うのが一般的。グラウト材には高い流動性や無収縮性、材料不分離性が求められる。
- プレミックス
- 混合して使用するものを事前に混合しておくことをいう。モルタルの袋物は、水以外の材料をプレミックスして袋に梱包した製品である。
- フロー試験
- セメントやモルタルに使用される試験方法のひとつ。コーンに詰めた試料のコーン引き上げ後の広がり(直径)をフロー値として測定する。フロー値はスラリーの降伏値を表す指標となる。降伏値が小さいほどフロー値は大きく水平流動性が高いことを示す。セルフレベリング材では、建築学会のJASS 15において、フロー試験が規定されている。
- プロテクト工法
- コンクリート構造物の補強や防食を目的とした工法の総称。梁、屋根、外壁等の施工部位や、グラウト材、樹脂含浸剤、FRP等の施工材料、また具体的な施工手順方法の違い等によって、様々な工法がある。
- ペースト
- 水とセメントを混合した建設材料のひとつ。コンクリートやモルタルと異なり、骨材(砂、砂利)が含まれない。下地調整材、仕上げ材、目地材等の多くの用途に使用される。袋物として流通しているものは、セメントに特殊な混和剤をプレミックスさせたものが多い。
- 膨張材
- 自己収縮の緩和やケミカルプレストレスの導入を目的として、コンクリート等に添加する膨張性の材料のこと。主に、材料の組成の違いによって、CSA系と石灰系に分けられる。また、アルミニウム粉末等の発泡剤を利用して膨張効果をもたせている材料もある。
- 補強
- 構造物の構造的、力学的な性能を、建設当時に保有していたよりも高い性能まで向上させることをいう。原状回復が主目的の補修とは異なる。部材の増設、床や壁の増厚、柱の巻立てなどが補強工法の例である。
- 補強材
- 補強の際に用いられる材料。増厚工法や鋼板巻き立て工法の際には、補強材または補強材の一部としてグラウト材を使用する。床の増厚には、高強度型のセルフレベリング材 も使用できる。
- ポリッシャー
- 主に床を磨く際に用いる研磨機。ワックス掛けなどに用いられることが多い。セルフレベリング材に発生する軽度な不具合、気泡や白華、風しわ等の除去にも使用できる。
- ポンプ圧送
- 生コンクリートやスラリーなどをポンプを使って施工部位まで送ること。コンクリート等のポンプ圧送のしやすさの度合いをポンパビリティという。ポンプ圧送をすると材料が分離しやすくなるため、圧送するコンクリートやスラリーには材料分離抵抗性が求められる。
- ポンプ中継
- ポンプ圧送したホースの筒先からコンクリートやスラリーをホッパーに受けて、再度または多段階でポンプ圧送を行うこと。高層建築等の圧送距離が長い場合に用いられる。圧送距離が長く、圧送回数が増えるほど、材料分離はより起こりやすくなる。
- 補修
- 劣化、損傷した構造物に対して、主に美観や耐久性などを実用上支障のない状態に回復させることをいう。ひび割れ補修や表面被覆、断面修復などが補修工法の例である。
- 補修材
- 補修の際に用いられる材料。コンクリート構造物にはモルタルが補修材として使用される場合が多い。断面修復やひび割れ注入の際には、補修材としてグラウト材を使用する。
マ行
- マスコンクリート
- 部材の断面寸法が大きい構造物に使用されるコンクリートのこと。マスコン。セメントの水和熱による温度ひび割れが発生しやすいため、温度上昇の少ない低熱型のコンクリートとする必要がある。マスコンに該当するかどうかの寸法は、土木学会や建築学会で目安を定められているが、それ以下の寸法の部材であっても温度ひび割れの発生が懸念される場合がある。
- 豆板
- コンクリートの打設の際、部分的にコンクリートが行き渡らず、型枠面に骨材が露出した状態になっている不具合のひとつ。あばた、巣、などともいう。
- 水セメント比
- コンクリートやモルタルを作る際の、水量とセメント量の比。水セメント比が小さいほど、圧縮強度は大きくなる。ただし発熱や自己収縮が大きくなるため、用途に応じた水セメント比を選ぶことが大切である。
- 無収縮グラウト材
- 収縮抑制または膨張効果をもたせて収縮が発生しないようにしたグラウト材。グラウト材は密閉空間に充填される材料であるため、無収縮グラウト材は自己収縮に対して無収縮であることを意味している。暴露環境では乾燥収縮が発生するため、例え無収縮グラウト材であっても無収縮にはならない。
- 無収縮モルタル
- モルタルに収縮抑制または膨張効果をもたせ、収縮が発生しないようにしたもの。一般的にグラウト材には無収縮性が求められるため、無収縮モルタルをベースにした無収縮グラウト材が使用される場合が多い。
- モルタル
- 水とセメントと骨材(細骨材)を混合した建設材料のひとつ。コンクリートと異なり、粗骨材(砂利)が含まれない。下地調整材、仕上げ材、目地材等の多くの用途に使用される。水以外をプレミックスした状態で、袋物として流通しているものが多い。
ヤ行
- 床材
- 建築材料を施工部位によって分類する際のひとつで、床を形成する材料をいう。セルフレベリング材は、床材のうちの下地調整材のひとつ。単に床材といった場合、床仕上げ材を差す場合が多い。
- 養生
- 打ち込んだコンクリートやモルタルなどに所定の圧縮強度や耐久性が得られるよう、保温や保湿を行うことをいう。セメント関連製品は、施工後に十分な養生を行うことが極めて大切である。
ラ行
- 流動性
- コンクリートやスラリーなどの流れ動きやすさを表す度合いをいう総合的な概念。セルフレベリング材の施工性やグラウト材の充填性を高めるためには、高い流動性が必要になる。練混ぜ水量を多くすれば流動性は高くなるが、強度の低下や材料分離が起こりやすくなるため、特に袋物を扱う際には注意しなければならない。
- レイタンス
- コンクリートやモルタルの硬化の際に、表面に浮き上がってくる脆弱層をいう。セメントや骨材に含まれる不純物から構成され、打継ぎの付着を妨げる。ブリーディングが多いほどレイタンスは発生しやすい。セルフレベリング材を施工する場合には、床の下地コンクリートに残ったレイタンスは必ず除去する必要がある。
- レオロジー
- 物質の変形と流動に関する科学、学問の分野のこと。ペーストやスラリー、生コンクリートなどは塑性と粘性をあわせもつ流体であり、レオロジーの取り扱う分野に属している。
- レベリング材
- セルフレベリング材を参照。
- 漏斗試験(ロート試験)
- 漏斗型の試験器に入れたモルタル等の流下試験を計測し、コンシステンシーを評価する試験方法。主に粘性(塑性粘度)を表す指標となる。試験方法は土木学会規準等によって規定され、モルタルではJ漏斗やP漏斗、コンクリートではO漏斗やV漏斗が使用される。
- ワーカビリティ
- コンクリートの打込みの作業のしやすさを表す度合いをいう。流動性や粘性のほか、材料分離に対する抵抗性など、さまざまな要素が関係する経験的な指標に近い。数値化はできないが、一般的にはスランプ値をワーカビリティの指標とする場合が多い。